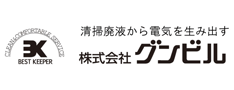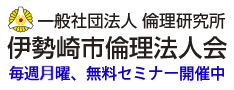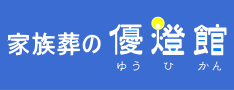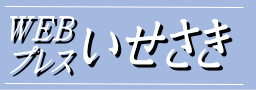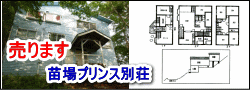生きていくために働かざるを得ない高齢者も(写真はイメージ)
アジア社会の高齢化に伴い「退職」の意味は「さらに働くこと」に
地元プロが翻訳 ニューヨークタイムズ社説8(2023年1月7日付)
米国の高級紙、ニューヨークタイムズ。その社説から、日本人にとって関心が深いと思われるテーマ、米国からみた緊張高まる国際情勢の捉え方など、わかりやすい翻訳でお届けしています(電子版掲載から本サイト掲載まで多少の時間経過あり)。伊勢崎市在住の翻訳家、星大吾さんの協力を得ました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
モトコ リッチ、ヒカリ ヒダ(アジア欄社説)
東京より
オオナミヨシヒトさんの望みは、引退して疲れた体を休めることだけだ。
毎朝1時半に起床し、車で1時間かけて東京湾の小島にある青果市場へ向かうオオナミさん(73)。キノコ、ショウガ根、サツマイモ、ダイコンなどの野菜を車に積み込みながら、15キロ以上ある箱を何度も持ち上げ、腰に負担をかける。その後、首都圏を走り回り、1日に10軒ほどレストランに納品する。
「体が許す限り、仕事を続けなければ」
オオナミさんはそう言って、朝、クリップボードに書かれた注文を確認しながら、市場を足早に歩く。
東アジアでは人口の減少にともない、若年労働者が減少しているため、オオナミさんのように70代まで働き続ける労働者が増えている。企業は彼らを必要とし、高齢者は仕事を必要としている。早期退職によって年金受給者が増え、アジア諸国の政府が退職者に毎月十分な生活費を支払うことが困難になる。
人口統計学者は何年も前から、富裕国に迫り来る“人口統計上の時限爆弾”について警鐘を鳴らしてきた。しかし、日本やその近隣諸国はすでにその影響を感じ始めている。政府や企業、そして何よりも高齢者が、高齢化社会がもたらすさまざまな影響に対処している。この変化が最も顕著に現れているのは彼らの職場である。
この年で働くのは「楽しくてやっているわけじゃない」と、オオナミさんはニンジンの箱をつめる。「でも、生きていくためにはしかたがない」。
特に、若年労働者に押されて早期退職を余儀なくされている高齢者にとっては、労働者需要によって新たな機会が与えられ、雇用主との関係も有利になる。今、高齢化が進む国々が取り組んでいるのは、高齢労働力という新たな現実と可能性にどう適応していくか、一方で、人々が貧困に陥ることなく退職できるようにするにはどうしたらよいかという問題である。
世界のどの国よりも早く高齢化が進んでいる東アジアでは、より柔軟な対応が急務となっている。日本、韓国、中国はいずれも、企業への補助金や退職金の調整など、人口の変動に対応するための政策変更に挑まなければならない状況にある。そして今、世界の他の地域でも、多くの国々が遠からず迎える同様の危機に対応するための指針をアジアに求めることになるだろう。
香港科技大学の社会科学教授であるスチュアート・ジーテル・バステン氏は、「パニックに陥って怯えながら走り回るだけか?それとも、"それは非常に複雑であり、我々は様々な方法で生活や制度を適応させなければならない"と認めるか」と言っている。
高齢者のニーズに適応
オオナミさんは、野菜配達を始めるよりも前に、会社員やタクシー運転手など、さまざまな職業を経験し、「やっぱり一人きりの運転手がいい」と思うようになった。戦後間もないころは、終身雇用で給料が保証され、定期的に昇進し、退職金も出るというのが一般的だったが、この決断によって、彼はずっと契約社員として働くことになった。
オオナミさんはトラック運転手として重い荷物を運ぶことが多かったが、50歳を過ぎたあたりから、それができなくなった。医師から「背骨の軟骨がすり減った」と言われたのだ。「箱を運ぶのは、体がとてもつらかった」とオオナミさんは言う。
小口配送の仕事を転々とし、15年ほど前に青果市場との契約が成立した。しかし、60歳の定年を前にしても、オオナミさんは仕事をやめるわけにはいかなかった。契約社員として働いてきたオオナミさんは、国民年金の基礎年金(月6万円、約477ドル)しか受け取れず、生活費をまかなうにはとても足りない。
東アジアで高齢者が「働き続けるしかない」と感じているのは日本だけではない。高齢者の貧困率が40%に迫る韓国では、65歳以上の高齢者のうち同じ割合が働き続けている。香港では、高齢者の8人に1人が働いている。日本では4分の1以上であり、米国では18%である。
日本や韓国では、こうした高齢者労働者を支援するために、派遣会社や労働組合が結成されている。経済的な理由で働かざるを得ない人も多いが、雇用主も彼らを頼りにするようになった。
人口統計学者が“超高齢化社会”と呼ぶものに対処するため、東アジアの政策立案者は当初、出生を促進し、労働力を補強するために移民法を改正することに重点を置いていた。しかし、出生率が急落し、多くの国が大規模な移民計画に抵抗したため、こうした対策は高齢化の流れを変えるには至らなかった。
そのため、雇用主は働き手を求めて必死になっている。例えば日本では、半数の企業が正社員の不足を訴え、高齢者がその穴を埋めるために参入している。アジア開発銀行研究所のオガワナオヒロ客員研究員は、「日本には未開発の労働力が多く眠っている」と指摘する。
東京の派遣会社「高齢社」は、求人票に「60歳以上」と明記している。ムラゼキフミオ社長は、雇用主が高齢者の雇用に前向きになっているとの見方を示した。「レンタカー会社やビルのコンシェルジュサービスは高齢者を雇いたがっている」とムラゼキ氏は言う。高齢の契約社員に人気のある仕事の一つとして、電気工事士やガス修理士が現場で顧客をサポートする間、サービスカーの助手席に座っているというものがある。ムラゼキ氏によると、契約社員は必要に応じて車を移動させ、企業は駐車違反や交通違反の罰金を避けることができるという。
東京にある集合住宅の不動産管理会社、東急コミュニティーでは、スタッフのほぼ半数が65歳以上だと人事部長のイケダヒロユキ氏は言う。年俸はわずか230万円、つまり17,146ドル以下である。この仕事は若い労働者には魅力的ではない。一方、高齢者は年金収入を補うために低賃金を受け入れている。
日本政府は現在、階段の手すりや休憩所の増設など、高齢者のための設備を導入する中小企業に補助金を出している。
東京郊外にある警察官の制服を生産しているグロリアは、人手不足のため6年前に定年制を廃止した。高齢者を支援するため、同社は玄関にスロープを設け、工場の床に張られていた電線を壁や天井に移動し、従業員の転倒を防いでいる。
グロリアはホームページで、「自分自身が辞めたいと思うまで働ける会社にしたい」と言っている。
宅配便の相川運送では、ドライバーの乗り降りをサポートするため、トラックにグリップハンドルを設置した。シンガポール国立大学の人類学・社会学准教授であるフォン・チーシ氏は、「職場環境は高齢者に優しくなければならない」と話す。「トレーニングの機会を提供し、柔軟な退職の機会を提供する必要がある」。
少ない年金でのやりくり
ソーシャルメディアで、ウェイトリフティングをしたり、スモールビジネスを成功させたりしている魅力的な中高年がよく紹介されている一方で、中国、香港、日本、韓国の高齢者は、低賃金の事務員、食料品店の店員、宅配便の運転手、警備員である場合が多い。
これらの国ではフルタイムの安定した雇用は比較的若い人に限られており、多くの高齢労働者は低い定年年齢によって長期雇用から退職を余儀なくされた後、不安定で低賃金の契約労働に従事することになる。定年退職後は、国が保障する年金では基本的な生活費をまかなえないのが普通である。日本、中国、韓国では、平均的な年金は月500ドル以下である。また、米国とは異なり、これらの地域では確定拠出年金制度(401k)はまだ普及していない。
労働力不足を解消し、年金の支払いを続けるために、政府は定年退職の年齢を引き上げようとしているが、これには抵抗もある。ニューヨークのペース大学で行政学と社会政策を教えるシェイエン・チェン氏は、「中国では、人民は怒っている」と言う。「フルタイムで働き、定年まで勤め上げたのに、もっと働けというのか、と」。
定年退職年齢引き上げの法制化に難色を示すのは、多くの場合、雇用者側である。東アジアで一般的な年功序列の給与体系では、企業はむしろ高齢の従業員への給与を払いたくないのであって、現役期間を延長したいわけではない。
「生産性が同じであっても、高齢者が長く在籍しているために高い賃金を支払わなければならないのであれば、その費用対効果は低くなる」と、オーストラリアのシドニーにある人口高齢化研究センターのフィリップ・オキーフ所長は述べている。
政府の支援が行き届かない中、自ら働き口を切り開く高齢者もいる。北京の国営冷蔵倉庫で働くリー・マンさん(67)は、45歳で退職を余儀なくされた。政府は、氷点下の気温の中で働き続けるのは危険だと告げたのだ。
リーさんは、カリフォルニアの映画学校に通う娘の学費と生活費のために、「人生の最盛期」でまだ働けると考えた。彼女はベビーシッターをしながら、魚の煮付けやカボチャと豚肉の炒め物などの手料理を近所の人に売り始めた。
「仕事に復帰したことで、不安は解消された」とリーさんは言う。しかし、最近、腰痛と高血圧に悩まされている。「そろそろ引退かな」。
野菜配達員のオオナミさんにとって、定年退職は夢のまた夢。離婚歴のある3児の父で、末っ子と2人暮らし。貯金もなく、健康維持のためにビタミン剤を飲んでいるという。「今は、働いていない生活など想像もつかない」と彼は言った。
朝が早いため、趣味に費やす時間はほとんどない。午後、家に帰ると、炒め物を作って、2匹のマルチーズに餌をやり、午後6時には眠りにつくのが常である。
"最後まで働かない方がいい"
スドウエイジさん(69)は、まだ引退する気にはなれなかった。
40年以上、天然ガス供給会社である東京ガスで、メンテナンスと工事の仕事に従事してきた。60歳で定年退職し、会社はピーク時の半分の給料で週4日勤務の契約を結んでくれた。しかし、65歳になると、会社はもう契約を延長しないという。
妻のカズエさんと二人で、のんびりと旅行ができるくらいの収入を得るために、須藤さんは仕事を続けたいと思った。スドウさんは、「働き続けたい」と思い、高齢社に登録し、東京のガスパイプライン会社「あすか」の契約社員として働いている。週に3日、ガス管の敷設や修理をしている地域を車で回り、個人宅を訪問し工事の案内をする。
あすかの社員は、10人に1人が65歳以上である。そのほとんどが60歳で定年退職し、その後、低賃金で契約社員として働いている。アスカのタバタカズユキマネージャーは、「常時高齢者を再雇用することで人員を補っている」と言う。
スドウさんは、田舎をあちこち旅して、新しい人に出会うのが楽しいという。毎日ゴルフをするよりも、好奇心旺盛で夢中になれる。「人それぞれ。自分にとってはそれがいい」。
奥さんは、彼が仕事をするときは必ず手作りの弁当を持たせてくれるし、彼が外に出ること、つまり、互いに「自分の時間」を持つことができるのを喜んでいる。しかし、「働きながら死ぬのは、とても悲しいことです」と彼女は付け加えた。「最後まで働いてはいけないんです」。
星大吾(ほしだいご):1974年生まれ、伊勢崎市中央町在住。伊勢崎第二中、足利学園(現白鳳大学足利高校)、新潟大学農学部卒業。白鳳大学法科大学院終了。2019年、翻訳家として開業。専門は契約書・学術論文。2022年、伊勢崎市の外国語児童のための日本語教室「子ども日本語教室未来塾」代表。同年、英米児童文学研究者として論文「The Borrowersにおける空間と時間 人文主義地理学的解読」(英語圏児童文学研究第67号)発表。問い合わせは:h044195@gmail.comへ。
1 2 3 4-1 4-2 5 6 7 8 9 10-1 10-2 11
アジア社会の高齢化に伴い「退職」の意味は「さらに働くこと」に
地元プロが翻訳 ニューヨークタイムズ社説8(2023年1月7日付)
米国の高級紙、ニューヨークタイムズ。その社説から、日本人にとって関心が深いと思われるテーマ、米国からみた緊張高まる国際情勢の捉え方など、わかりやすい翻訳でお届けしています(電子版掲載から本サイト掲載まで多少の時間経過あり)。伊勢崎市在住の翻訳家、星大吾さんの協力を得ました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
モトコ リッチ、ヒカリ ヒダ(アジア欄社説)
東京より
オオナミヨシヒトさんの望みは、引退して疲れた体を休めることだけだ。
毎朝1時半に起床し、車で1時間かけて東京湾の小島にある青果市場へ向かうオオナミさん(73)。キノコ、ショウガ根、サツマイモ、ダイコンなどの野菜を車に積み込みながら、15キロ以上ある箱を何度も持ち上げ、腰に負担をかける。その後、首都圏を走り回り、1日に10軒ほどレストランに納品する。
「体が許す限り、仕事を続けなければ」
オオナミさんはそう言って、朝、クリップボードに書かれた注文を確認しながら、市場を足早に歩く。
東アジアでは人口の減少にともない、若年労働者が減少しているため、オオナミさんのように70代まで働き続ける労働者が増えている。企業は彼らを必要とし、高齢者は仕事を必要としている。早期退職によって年金受給者が増え、アジア諸国の政府が退職者に毎月十分な生活費を支払うことが困難になる。
人口統計学者は何年も前から、富裕国に迫り来る“人口統計上の時限爆弾”について警鐘を鳴らしてきた。しかし、日本やその近隣諸国はすでにその影響を感じ始めている。政府や企業、そして何よりも高齢者が、高齢化社会がもたらすさまざまな影響に対処している。この変化が最も顕著に現れているのは彼らの職場である。
この年で働くのは「楽しくてやっているわけじゃない」と、オオナミさんはニンジンの箱をつめる。「でも、生きていくためにはしかたがない」。
特に、若年労働者に押されて早期退職を余儀なくされている高齢者にとっては、労働者需要によって新たな機会が与えられ、雇用主との関係も有利になる。今、高齢化が進む国々が取り組んでいるのは、高齢労働力という新たな現実と可能性にどう適応していくか、一方で、人々が貧困に陥ることなく退職できるようにするにはどうしたらよいかという問題である。
世界のどの国よりも早く高齢化が進んでいる東アジアでは、より柔軟な対応が急務となっている。日本、韓国、中国はいずれも、企業への補助金や退職金の調整など、人口の変動に対応するための政策変更に挑まなければならない状況にある。そして今、世界の他の地域でも、多くの国々が遠からず迎える同様の危機に対応するための指針をアジアに求めることになるだろう。
香港科技大学の社会科学教授であるスチュアート・ジーテル・バステン氏は、「パニックに陥って怯えながら走り回るだけか?それとも、"それは非常に複雑であり、我々は様々な方法で生活や制度を適応させなければならない"と認めるか」と言っている。
高齢者のニーズに適応
オオナミさんは、野菜配達を始めるよりも前に、会社員やタクシー運転手など、さまざまな職業を経験し、「やっぱり一人きりの運転手がいい」と思うようになった。戦後間もないころは、終身雇用で給料が保証され、定期的に昇進し、退職金も出るというのが一般的だったが、この決断によって、彼はずっと契約社員として働くことになった。
オオナミさんはトラック運転手として重い荷物を運ぶことが多かったが、50歳を過ぎたあたりから、それができなくなった。医師から「背骨の軟骨がすり減った」と言われたのだ。「箱を運ぶのは、体がとてもつらかった」とオオナミさんは言う。
小口配送の仕事を転々とし、15年ほど前に青果市場との契約が成立した。しかし、60歳の定年を前にしても、オオナミさんは仕事をやめるわけにはいかなかった。契約社員として働いてきたオオナミさんは、国民年金の基礎年金(月6万円、約477ドル)しか受け取れず、生活費をまかなうにはとても足りない。
東アジアで高齢者が「働き続けるしかない」と感じているのは日本だけではない。高齢者の貧困率が40%に迫る韓国では、65歳以上の高齢者のうち同じ割合が働き続けている。香港では、高齢者の8人に1人が働いている。日本では4分の1以上であり、米国では18%である。
日本や韓国では、こうした高齢者労働者を支援するために、派遣会社や労働組合が結成されている。経済的な理由で働かざるを得ない人も多いが、雇用主も彼らを頼りにするようになった。
人口統計学者が“超高齢化社会”と呼ぶものに対処するため、東アジアの政策立案者は当初、出生を促進し、労働力を補強するために移民法を改正することに重点を置いていた。しかし、出生率が急落し、多くの国が大規模な移民計画に抵抗したため、こうした対策は高齢化の流れを変えるには至らなかった。
そのため、雇用主は働き手を求めて必死になっている。例えば日本では、半数の企業が正社員の不足を訴え、高齢者がその穴を埋めるために参入している。アジア開発銀行研究所のオガワナオヒロ客員研究員は、「日本には未開発の労働力が多く眠っている」と指摘する。
東京の派遣会社「高齢社」は、求人票に「60歳以上」と明記している。ムラゼキフミオ社長は、雇用主が高齢者の雇用に前向きになっているとの見方を示した。「レンタカー会社やビルのコンシェルジュサービスは高齢者を雇いたがっている」とムラゼキ氏は言う。高齢の契約社員に人気のある仕事の一つとして、電気工事士やガス修理士が現場で顧客をサポートする間、サービスカーの助手席に座っているというものがある。ムラゼキ氏によると、契約社員は必要に応じて車を移動させ、企業は駐車違反や交通違反の罰金を避けることができるという。
東京にある集合住宅の不動産管理会社、東急コミュニティーでは、スタッフのほぼ半数が65歳以上だと人事部長のイケダヒロユキ氏は言う。年俸はわずか230万円、つまり17,146ドル以下である。この仕事は若い労働者には魅力的ではない。一方、高齢者は年金収入を補うために低賃金を受け入れている。
日本政府は現在、階段の手すりや休憩所の増設など、高齢者のための設備を導入する中小企業に補助金を出している。
東京郊外にある警察官の制服を生産しているグロリアは、人手不足のため6年前に定年制を廃止した。高齢者を支援するため、同社は玄関にスロープを設け、工場の床に張られていた電線を壁や天井に移動し、従業員の転倒を防いでいる。
グロリアはホームページで、「自分自身が辞めたいと思うまで働ける会社にしたい」と言っている。
宅配便の相川運送では、ドライバーの乗り降りをサポートするため、トラックにグリップハンドルを設置した。シンガポール国立大学の人類学・社会学准教授であるフォン・チーシ氏は、「職場環境は高齢者に優しくなければならない」と話す。「トレーニングの機会を提供し、柔軟な退職の機会を提供する必要がある」。
少ない年金でのやりくり
ソーシャルメディアで、ウェイトリフティングをしたり、スモールビジネスを成功させたりしている魅力的な中高年がよく紹介されている一方で、中国、香港、日本、韓国の高齢者は、低賃金の事務員、食料品店の店員、宅配便の運転手、警備員である場合が多い。
これらの国ではフルタイムの安定した雇用は比較的若い人に限られており、多くの高齢労働者は低い定年年齢によって長期雇用から退職を余儀なくされた後、不安定で低賃金の契約労働に従事することになる。定年退職後は、国が保障する年金では基本的な生活費をまかなえないのが普通である。日本、中国、韓国では、平均的な年金は月500ドル以下である。また、米国とは異なり、これらの地域では確定拠出年金制度(401k)はまだ普及していない。
労働力不足を解消し、年金の支払いを続けるために、政府は定年退職の年齢を引き上げようとしているが、これには抵抗もある。ニューヨークのペース大学で行政学と社会政策を教えるシェイエン・チェン氏は、「中国では、人民は怒っている」と言う。「フルタイムで働き、定年まで勤め上げたのに、もっと働けというのか、と」。
定年退職年齢引き上げの法制化に難色を示すのは、多くの場合、雇用者側である。東アジアで一般的な年功序列の給与体系では、企業はむしろ高齢の従業員への給与を払いたくないのであって、現役期間を延長したいわけではない。
「生産性が同じであっても、高齢者が長く在籍しているために高い賃金を支払わなければならないのであれば、その費用対効果は低くなる」と、オーストラリアのシドニーにある人口高齢化研究センターのフィリップ・オキーフ所長は述べている。
政府の支援が行き届かない中、自ら働き口を切り開く高齢者もいる。北京の国営冷蔵倉庫で働くリー・マンさん(67)は、45歳で退職を余儀なくされた。政府は、氷点下の気温の中で働き続けるのは危険だと告げたのだ。
リーさんは、カリフォルニアの映画学校に通う娘の学費と生活費のために、「人生の最盛期」でまだ働けると考えた。彼女はベビーシッターをしながら、魚の煮付けやカボチャと豚肉の炒め物などの手料理を近所の人に売り始めた。
「仕事に復帰したことで、不安は解消された」とリーさんは言う。しかし、最近、腰痛と高血圧に悩まされている。「そろそろ引退かな」。
野菜配達員のオオナミさんにとって、定年退職は夢のまた夢。離婚歴のある3児の父で、末っ子と2人暮らし。貯金もなく、健康維持のためにビタミン剤を飲んでいるという。「今は、働いていない生活など想像もつかない」と彼は言った。
朝が早いため、趣味に費やす時間はほとんどない。午後、家に帰ると、炒め物を作って、2匹のマルチーズに餌をやり、午後6時には眠りにつくのが常である。
"最後まで働かない方がいい"
スドウエイジさん(69)は、まだ引退する気にはなれなかった。
40年以上、天然ガス供給会社である東京ガスで、メンテナンスと工事の仕事に従事してきた。60歳で定年退職し、会社はピーク時の半分の給料で週4日勤務の契約を結んでくれた。しかし、65歳になると、会社はもう契約を延長しないという。
妻のカズエさんと二人で、のんびりと旅行ができるくらいの収入を得るために、須藤さんは仕事を続けたいと思った。スドウさんは、「働き続けたい」と思い、高齢社に登録し、東京のガスパイプライン会社「あすか」の契約社員として働いている。週に3日、ガス管の敷設や修理をしている地域を車で回り、個人宅を訪問し工事の案内をする。
あすかの社員は、10人に1人が65歳以上である。そのほとんどが60歳で定年退職し、その後、低賃金で契約社員として働いている。アスカのタバタカズユキマネージャーは、「常時高齢者を再雇用することで人員を補っている」と言う。
スドウさんは、田舎をあちこち旅して、新しい人に出会うのが楽しいという。毎日ゴルフをするよりも、好奇心旺盛で夢中になれる。「人それぞれ。自分にとってはそれがいい」。
奥さんは、彼が仕事をするときは必ず手作りの弁当を持たせてくれるし、彼が外に出ること、つまり、互いに「自分の時間」を持つことができるのを喜んでいる。しかし、「働きながら死ぬのは、とても悲しいことです」と彼女は付け加えた。「最後まで働いてはいけないんです」。
星大吾(ほしだいご):1974年生まれ、伊勢崎市中央町在住。伊勢崎第二中、足利学園(現白鳳大学足利高校)、新潟大学農学部卒業。白鳳大学法科大学院終了。2019年、翻訳家として開業。専門は契約書・学術論文。2022年、伊勢崎市の外国語児童のための日本語教室「子ども日本語教室未来塾」代表。同年、英米児童文学研究者として論文「The Borrowersにおける空間と時間 人文主義地理学的解読」(英語圏児童文学研究第67号)発表。問い合わせは:h044195@gmail.comへ。
1 2 3 4-1 4-2 5 6 7 8 9 10-1 10-2 11